糖尿病と診断されたけど症状は軽い?まずは他の医師にも相談してみよう

糖尿病とは
糖尿病とは、インスリンというホルモンの作用不足により、血液中のブドウ糖濃度(血糖値)が慢性的に高くなる病気です。
糖尿病の種類
糖尿病は4種類に分類されます。
1型糖尿病
1型糖尿病では、膵臓の細胞が破壊され、インスリンがほとんど分泌されなくなり、血糖値が高くなります。
2型糖尿病
2型糖尿病では、遺伝的な要因に、食べすぎや運動不足といった生活習慣が加わることで、インスリンの分泌が低下したり、効きが悪くなったりします。
日本の糖尿病患者の多くはこの2型糖尿病に該当します。
その他の特定の機序、疾患による糖尿病
膵臓の病気、肝臓病、内分泌疾患など、またステロイドなど薬剤の副作用により、糖尿病が発症することがあります。
妊娠糖尿病
妊娠中に初めて発見または発症した、妊娠に関連した糖代謝異常です。
出産後に血糖値が正常に戻ることもありますが、将来的に2型糖尿病を発症するリスクが高まります。
糖尿病の原因
糖尿病の主な原因は、インスリンの作用不足、自己免疫疾患、生活習慣(食べ過ぎ、運動不足、ストレスなど)などです。
遺伝的な体質で糖尿病になることもあります。
糖尿病の症状
初期はほとんど症状がありません。
血糖値がかなり高くなると、喉の渇き、頻尿、体のだるさ、体重減少などの症状が発生します。
血糖値が高い状態が長く続くと、全身の血管が傷つき、心臓病、腎不全、脳卒中などの合併症を引き起こす可能性があります。
HbA1cの基準値の扱いに差が出やすい
糖尿病の診断においては、血糖値(瞬間的な血糖値)の他にHbA1c(ヘモグロビンA1c)も重要視されていますが、HbA1cの基準値の解釈には差が出やすいです。
HbA1cとは、過去1~2ヶ月の血糖値の平均をさします。瞬間的な血糖値と一致しないこともあります。HbA1cが6.5%以上は糖尿病の可能性が高く、血糖値が正常範囲内でも食事内容によってHbA1cが高くなることがあります。
HbA1c値の扱いに差が出やすいことには下記のことが関係しています。
患者の年齢や合併症の有無
HbA1c値は、患者の年齢や合併症の有無によって異なります。一般的に、糖尿病合併症を予防するための目標値は7.0%未満とされますが、合併症のリスクが高い場合は、より厳格な目標(6.0%未満)が設定されることもあります。
赤血球の寿命
HbA1cは赤血球の寿命に影響を受けるため、貧血などの血液疾患があると、実際の平均血糖値とは異なる値を示すことがあります。例えば、溶血性貧血など、赤血球の寿命が短くなる病態では、HbA1cが実際よりも低く出る可能性があります。
古い基準値との混同
日本ではHbA1c測定の国際標準化に対応するため、JDS値からNGSP値へと変更されました。現在はNGSP値で統一されていますが、かつての基準値が混在しており、解釈の混乱を招くことがあります。
健康診断での基準
医療機関によっては指導の基準値が異なる場合もあります。HbA1cが6.5%以上で糖尿病と診断されますが、特定健診などでは5.6%以上で「特定保健指導」の対象となるケースもあります。
糖尿病の治療
糖尿病の基本治療は、食事療法、運動療法、薬物療法の3つです。
このような治療を行うことで、血糖値を適切にコントロールし、合併症を防ぐことができます。食事療法と運動療法を基本とし、必要に応じて経口血糖降下薬やインスリン注射などの薬物療法を組み合わせて行います。
食事療法
糖尿病治療の根幹をなす最も重要な治療法です。現在の食生活を見直し、体重管理や適切なエネルギーバランスを意識することが大切です。

運動療法
食後の血糖値上昇を抑え、インスリンの効きを良くする効果があります。継続することで体脂肪が減り、血圧や中性脂肪の改善にもつながります。有酸素運動やレジスタンス運動(スクワット、腹筋運動など)を組み合わせて行います。
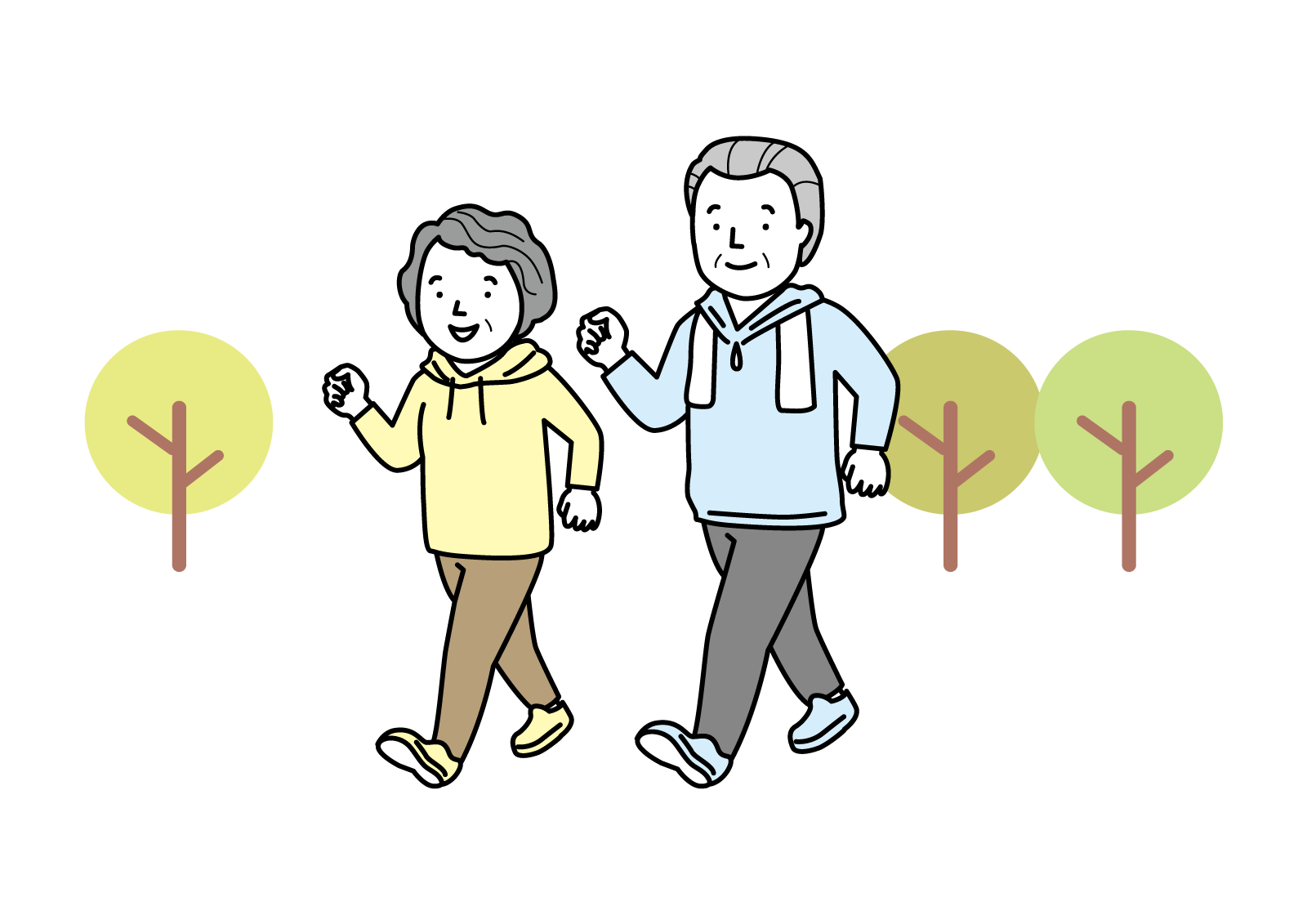
薬物療法
食事療法と運動療法だけでは血糖値が十分にコントロールできない場合に、薬物療法が加わります。
経口血糖降下薬はインスリンの分泌を促したり、糖の吸収を穏やかにしたり、尿への排泄を促したりします。複数の種類の薬を組み合わせて使う場合もあります。
また、体内に足りないインスリンを補うためにインスリン注射を行います。自己注射で行うのが一般的です。

内科医・糖尿病専門医の意見の取り入れ方
糖尿病でお悩みの場合はまず、かかりつけ医に相談しましょう。かかりつけ医から糖尿病専門医を紹介することもあり、医師連携で治療方針を決めることがあります。
診断や治療方針に不安がある場合は、セカンドオピニオンを受けることもおすすめです。
セカンドオピニオンとは英語の「Second Opinion」で、「第二の意見」と意味をしています。ある病気や症状に対して、多くの医師から意見を聞き、最適な対策を選んでいくのです。
現在診療を受けている医師とは別の医療機関の医師に相談して、最善の治療法を選択できます。
